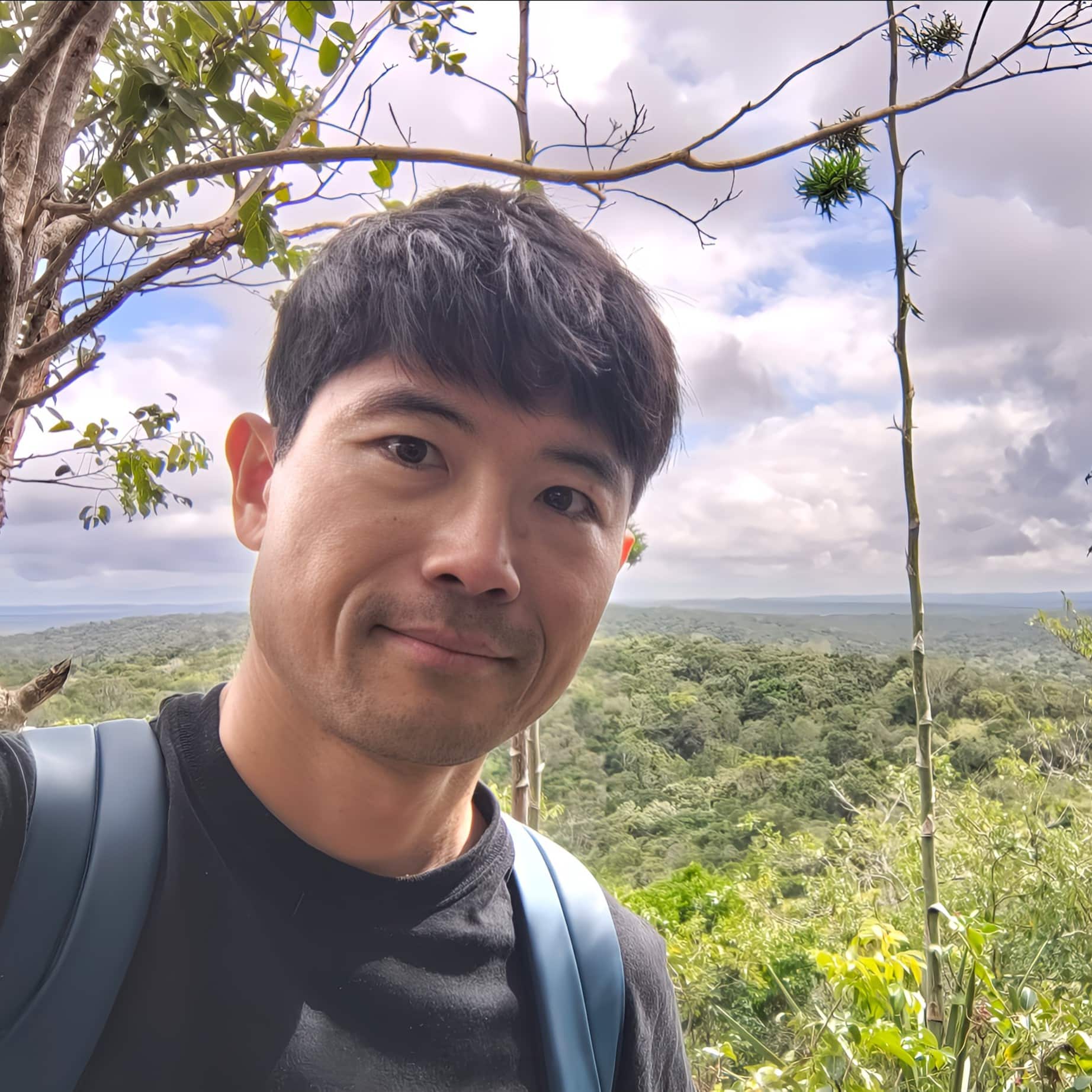メソアメリカとヨーロッパを繋げたものとは。
メキシコ在住15年目、
「メキシコの素顔を世界に!」
をモットーに、
メキシコ公認ツアーガイド兼ドライバーの岩﨑コウです。
こうして繋がった2大陸

雑談(笑)
前回はこちら~👇
どうやってカトリックは根付いた?
おはようございます!
梅雨が明け、
暑くなっている日本だと思いますが、
皆さん、
いかがお過ごしでしょうか?
僕は昨日1日土曜日に、
ケレタロ州にあるシエラ・ゴルダという国定公園に行ってきたんです。
地図でルートを見ただけで、
計画らしい計画はナシで行ったら、
結局900キロも走っていて、
家に着いたのは日付が変わった1時でした。(苦笑)
本当は一ヶ所行きたいところがあったのですが、
コロナで封鎖されていて行けずじまい。
でも改めて自然パワーを存分に浴びることができた旅だったので、
大大大満足です。(笑)
メキシコからカトリックは外せない
メソアメリカとヨーロッパをつなげたもの。
カトリックの話題は、
最初はちょこっと書く予定だったのですが、
気が付いたらもう3回目です。(笑)
カトリックは、
日本ではあまり馴染みが無いかもしれませんが?、
メキシコの世界観を知るには、
少し知っておいた方が良いかもしれません。
かく言う僕も、
全く宗教気がないんです。(苦笑)
でも仏教は少し勉強したいと思っています。
勉強といっても、
お坊さんが使うような経典のようなものを読めるようになりたい、
ではなくて、
仏教的な考え方ですね。
実生活でも役立つことが多いと思うんです。
そんなわけで、
以前は僕の中で「全く興味が無かった」話題、
「カトリック教」ですが、
メキシコ史上では無視できないものですので、
メキシコを「知る」という観点で書いてみることにしました~。
ヨーロッパとアメリカ大陸の交わり
ヨーロッパとメソアメリカ、
月とスッポンの両者がどのように交わったのか。
それには、
メシカ人が信じていた「神々の母トナンツィン」の聖地で、
メソアメリカの人達と同じ肌の色の
「褐色の聖母グアダルーペ」
を“出現させ”、
両者を紐づけたのです。
しかもです、
その褐色の聖母との出会いに、
スペイン人ではなく、
“地元の人”を使ったのです。
でもどうやって?
“使った”という表現が正しいのか分かりませんが、
カトリックの“言い伝え”を信じない、
非信者の立場からするとそうなると思います。
メキシコに現れた“聖人”
その“地元の人”というのは、
フアン・ディエゴといいます。
この名前はスペイン語の名前で、
本来の名前は、
クアウトゥラトアツィン
(Cuautlatoatzin)
または、
クアウトゥロアトアツィン
(Cuauhtloatoatzin)、
クアウトゥラトウァック
(Cuauhtlatohuac)
というように、
参考文献によって違うんです。(苦笑)
最初のクアウトゥラトアツィンが、
学校の教授から教えてもらったものなので、
それが正しいとします。

☝この人
1474年に生まれたフアン・ディエゴさんは、
もともとペタテ(Petate)という、
ござのようなものを作る人だったんです。

☝☝☝これです。
彼の家はメキシコシティ中心部から、
北方面に20数キロ離れたクアウティトランという所にあります。
この道のりを、
ペタテを担いで、
中心部のトラテロルコの市場で売っていたんですね。

☝☝☝クアウティトランとトラテロルコ・直線距離で25キロぐらい
(グーグルマップ)
ちなみに、今も彼の家跡が史跡として保存されています。

グアダルーペ寺院に行くワケ
言い伝えによると、
1531年の12月9日土曜日、
57歳だった彼はテペヤック山付近を歩いていました。
すると変わった“歌”のようなものが聞こえてきたらしいんです。
山の上の方を見上げると太陽が燦燦と輝いています。
すると、
そこに「聖母」がいるではないですか!?
フアン・ディエゴは聖母に近寄って挨拶をします。
すると聖母は、
「そこにあるトナンツィンの聖地の一角に寺院を建て、
そしてこの事を大司教に伝えるように」
と言うのです。
フアン・ディエゴはその日のうちに大司教に伝えます。
しかし、その大司教は信じません。
彼の名はフアン・デ・スマラガ。
メキシコで最初の大司教です。

☝植民地の初代大司教フアン・デ・スマラガ
その場に戻ると2度目の聖母の出現を目にします。
そして再び大司教スマラガに伝えます。
まだ信じてもらえません。
何か証拠を持って来るようにフアン・ディエゴに伝えると、
翌日10日日曜日にその場所に戻ります。
3度目の“出現”です。
そこで聖母に何か貰えるように頼みます。
すると翌日月曜日に再び来るように言います。
翌日11日月曜日。
フアン・ディエゴは一緒に住む叔父が体調を崩してしまい、
聖母に“会いに行く”ことができません。
12月12日火曜日、
その場所に再び行くと4度目の“出現”があり、
聖母はフアンに“花”を大司教に持って行くよう伝えます。
その花というのは“バラ”だったようです。
バラはバラでも、
その季節のものでなければ、
その地域に咲くものでもないような花だったようです。
フアンは持っていたアジァテ(Ayate)
というネットというか布のようなもので
その花を包むと、
そのまま誰の目にも触れないように大司教の元に持って行きます。
そして大司教の前でそれを広げるや否や、
「褐色の聖母グアダルーペ」像が現れたのです。

☝これがその一幕。
右がアジャテを広げるフアン・ディエゴ
ちょっと見えづらいかもしれまえんが、
聖母グアダルーペ像が描かれています。
左が初代大司教スマラガ
手前に“バラ”も見えます。
(岩﨑撮影)
さらには、
この日、
フアン・ディエゴと暮らす叔父の元に
5度目の“出現”があったとされています。
文献によっては4度目までのものあり、
真相は“わかりません”。(笑)
だ・か・ら、
毎年12月12日に、
メキシコ各地から、
遠い所では何百キロも自転車や歩いて、
このグアダルーペ寺院に巡礼に行くのです。

☝こんな感じで巡礼者が高速道路を進みます。
グアダルーペ寺院のはじまり
その後、
大司教スマラガは、
聖母グアダルーペがフアン・ディエゴに伝えたように、
メシカの神トナンツィンの聖地であり、
現在のグアダルーペ寺院の一角にある
Capilla de indios
(インディオの教会)
がある場所に、
小さな社(やしろ)を建てるのです。
これがグアダルーペ寺院で最も古い建造物、
とされています。
ここからグアダルーペ寺院の歴史は始まったんですね。

☝インディオ教会・右下にあるのはフアン・ディエゴ像(岩﨑撮影)
フアン・ディエゴは、
その年1531年から死去する1548年まで、
この社に住んだとされています。


☝☝☝奥の十字架が示す場所が、当時フアン・ディゴが住んでいた場所とされています。
日本は室町時代、信長の時代に入る手前、修道士フランシスコ・ザビエルが日本に来る1年前です。
(岩﨑撮影)
このように、
メシカの神々の母「トナンツィン」と、
メソアメリカバージョンに仕立てた
カトリックの「褐色の聖母グアダルーペ」を、
地元の人物フアン・ディエゴを“使い”、
繋げたのです。
ここからメソアメリカでの、
“精神の征服”が始まり、
現代のカトリックの国家としての礎ができたのです。
つづきはこちら~👇
グアダルーペ寺院の建設メキシコ発【キオテ通信】バックナンバーはこちら!
一番下に関連記事が表示されるようになりました~
画面を一番下👇👇👇までスクロール~
【お一人のお客様同士のライドシェア】
お得なキオテのライドシェア詳細はこちらSNSにてメキシコの写真と動画を多数アップしています!
#MexicoCompleteTravel
20年近くメキシコの社会にどっぷり浸かり生活している私から見た「メキシコの素顔」を、文章、写真、動画でご紹介しております。
ぜひフォローをお願いします!
View this post on Instagram
メキシコ旅行相談窓口
【人生のリバイバルコーチング事業】
私岩﨑はICF(インターナショナル・コーチング・フェデレーション)認定ライフコーチング業も営んでいます。
皆さんが一度限りの人生、限りある人生を有意義に生きられるようお手伝いさせて頂きます。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。