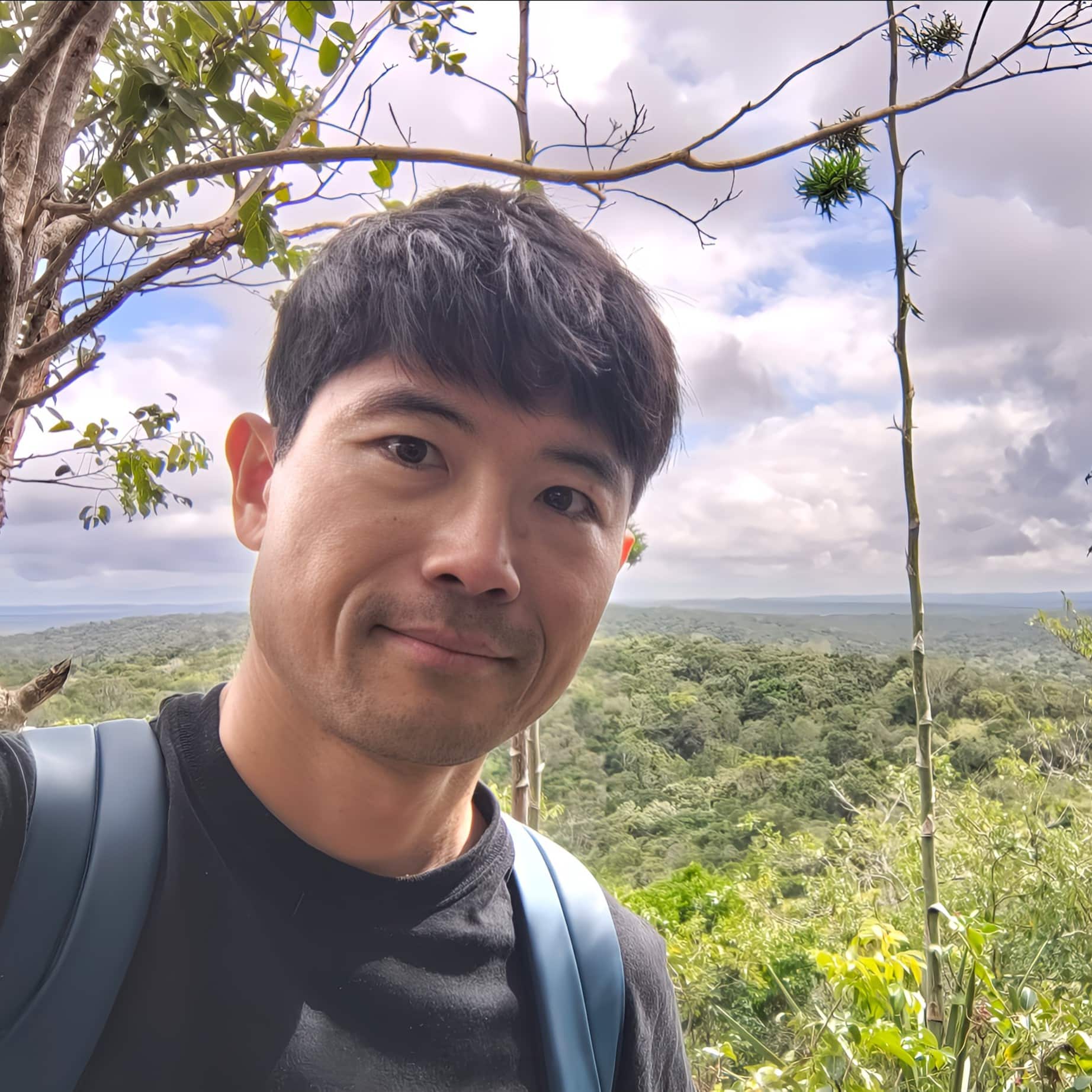パペル・ピカド・あのメキシコの飾りの正体は。
メキシコ在住15年目、
「メキシコの素顔を世界に!」
をモットーに、
メキシコ公認ツアーガイド兼ドライバーの岩﨑コウです。
パペル・ピカド・あのメキシコの飾りの正体は。

メキシコにいらした事がある方でしたら、
一度はご覧になったことがあるでしょう。
メキシコにいらした事がない方も、
リメンバーミーをご覧になられた方でしたら、
ご存知の方も多いと思います。
切絵のような飾りですね。
特に独立記念日や、
死者の日では欠かす事の出来ない飾りです。
パペル・ピカドというんですが、
パペルは紙、
ピカドは突き刺す、
という意味です。
公式な資料で、
これに関する情報が少ないので、
(☝僕の調査不足です・・・)
その起源について十分な説明ができませんので、
ご了承下さい。
写真にも出て来る、
現在のカタチになったのは、
実は割と最近なんです。

現在のスタイルの元になったのは、
中国の剪紙(せんし)です。
切絵ですね。

ヨーロッパには16世紀頃からあったようですが、
メキシコに伝わるのは19世紀。
16世紀当時のヨーロッパでは、
パペル・コルタド(切り紙)と呼ばれていました。
19世紀に入り、
プエブラのウィスコロトゥラ村の農夫や工夫たちが、
仕事場で食べ物を買う際に、
商品が包まれていたのが薄葉紙、
メキシコではパペル・チノと呼ばれているんですが、
意味はそのままです。
中国紙。(笑)
現在は、
屋外に飾る場合には、
風雨への耐久性の為にプラスチック製が主流です。
手先が器用な工夫たちは、
この紙を使って切絵を作り始めます。

☝☝☝見渡せば、至る所にパペル・ピカド(屋外はプラスチック製)
出来たものを、
仕事場や、
隣町の住民に売り始めたのが始まりなんです。
世代を超え、
1930年頃からプエブラ、トラスカラ州で流行り始めます。
メキシコシティで一般的になったのは1960年代です。
元来は、
中国の剪紙同様、
ハサミを使っていたようですが、
その後はノミが主流に、
現在は工業製品として型で切り取る製品が多くなっているようです。
メキシコシティの老舗では、
価格も価値も安価な工業製品が主流になり、
手作り工芸品の伝統の消滅を危惧しているそうです。

現在の手作りものは、
ノミを使うのですが、
ご想像頂けるとおもいますが、
「紙に突き刺す」んですね。
これをPicado(ピカド)というんです。

で、
ここからは、
現代のパペル・ピカドと繋げていいものか、
僕はちょっと悩んでいるんですが、
一応説明だけさせて頂きます。

スペイン人が入って来る以前の時代、
メソアメリカ時代には、
アマテ紙という、
イチジク属などの樹皮からつくった紙を使っていたんです。

これを切り抜いて?
飾りにしていたようですが、
これが死者の日用の飾りとして使われていたのか、
そしてどのようあデザインで色付けがされていたのか、
ちょっとまだちゃんとした情報に辿り着けていないんです。(謝)
☝また調べます。(苦笑)
現代のものは色とりどりですが、
色にも意味合いがあるようです。
青は命を与える水、
黒は死者の世界である地下の世界、
橙は悲嘆、
紫はカトリック教、
白は子供、
赤はお産で亡くなった女性、
緑は若者、
黄色はお年寄り、
を象徴します。

ただ、
悲嘆や亡くなった女性といっても、
現代ではパーティーなどでも使われますから、
このような意味合いというのは、
現代においては重要視されていないよう思われます。
たとえ、
メソアメリカの習慣に端を発するものとしても、
その形は大きく変わってしまっているようです。
近年、
日本の情報サイトでも、
メキシコのお土産リストにランクインしているパペル・ピカド。
ご興味がりましたら、
現代パペル・ピカド発祥の地にお連れすることもできます。
どうしても時間が取れない場合には、
メキシコシティの老舗にお連れします。
できる事なら、
工芸品の伝統を守るためにも、
手作りのものをお求め頂く事をお願いさせて頂きたいです~。(笑)
ではまた。
メキシコ発【キオテ通信】バックナンバーはこちら!
一番下に関連記事が表示されるようになりました~
画面を一番下👇👇👇までスクロール~
<strong>【お一人のお客様同士のライドシェア】</strong>
お得なキオテのライドシェア詳細はこちら <h2 style=”text-align: center;”><span style=”color: #000080;”><strong>SNSにてメキシコの写真と動画を多数アップしています!</strong></span></h2><h3><span style=”color: #000080;”><strong>#MexicoCompleteTravel</strong></span></h3>
20年近くメキシコの社会にどっぷり浸かり生活している私から見た<strong>「メキシコの素顔」</strong>を、文章、写真、動画でご紹介しております。
ぜひフォローをお願いします!
<h3><span style=”color: #000080;”><strong>Facebook</strong></span></h3>
<div class=”fb-page” data-href=”https://www.facebook.com/mexicoct” data-tabs=”timeline” data-width=”370″ data-height=”” data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true”>
<blockquote class=”fb-xfbml-parse-ignore” cite=”https://www.facebook.com/mexicoct”><a href=”https://www.facebook.com/mexicoct”>Mexico Complete Travel</a></blockquote>
</div>
<h3><span style=”color: #000080;”><strong>Instagram</strong></span></h3>
<blockquote class=”instagram-media” style=”background: #FFF; border: 0; border-radius: 3px; box-shadow: 0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width: 540px; min-width: 326px; padding: 0; width: calc(100% – 2px);” data-instgrm-permalink=”https://www.instagram.com/p/CN-_NN2JOBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” data-instgrm-version=”14″>
<div style=”padding: 16px;”>
<div style=”display: flex; flex-direction: row; align-items: center;”>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;”></div>
<div style=”display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;”>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;”></div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;”></div>
</div>
</div>
<div style=”padding: 19% 0;”></div>
<div style=”display: block; height: 50px; margin: 0 auto 12px; width: 50px;”></div>
<div style=”padding-top: 8px;”>
<div style=”color: #3897f0; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: 550; line-height: 18px;”>View this post on Instagram</div>
</div>
<div style=”padding: 12.5% 0;”></div>
<div style=”display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;”>
<div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);”></div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;”></div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);”></div>
</div>
<div style=”margin-left: 8px;”>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;”></div>
<div style=”width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);”></div>
</div>
<div style=”margin-left: auto;”>
<div style=”width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);”></div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);”></div>
<div style=”width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);”></div>
</div>
</div>
<div style=”display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;”>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;”></div>
<div style=”background-color: #f4f4f4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;”></div>
</div>
<p style=”color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; line-height: 17px; margin-bottom: 0; margin-top: 8px; overflow: hidden; padding: 8px 0 7px; text-align: center; text-overflow: ellipsis; white-space: nowrap;”><a style=”color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” href=”https://www.instagram.com/p/CN-_NN2JOBx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” target=”_blank” rel=”noopener”>A post shared by Mexico Complete Travel(岩﨑コウ) メキシコ政府公認観光ガイド&ICF認定ライフコーチ (@koiwasaki.mex)</a></p>
</div></blockquote>
<script async src=”//www.instagram.com/embed.js”></script>
<h2 style=”text-align: center;”><strong>メキシコ旅行相談窓口</strong></h2>
<strong>【人生のリバイバルコーチング事業】</strong>
私岩﨑はICF(インターナショナル・コーチング・フェデレーション)認定ライフコーチング業も営んでいます。
皆さんが一度限りの人生、限りある人生を有意義に生きられるようお手伝いさせて頂きます。
詳しくはこちらのホームページをご覧ください。
<script async defer crossorigin=”anonymous” src=”https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v14.0″ nonce=”N9vkly0U”></script>